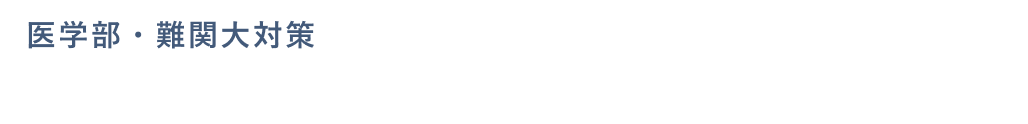新シリーズ。物理の学習法でオススメのものは?

本日もアテナイブログをお読みくださり、ありがとうございます。早いもので、2021年も、もう大晦日を迎えました。年末年始も休みなく猛勉強する人や、大晦日と元旦だけは家族と休養してリフレッシュを図る人など、思い思いの過ごし方をなさると思います。
来年は、寅年ですね。皆様、良いお年をお迎えください。来年が、皆さまにとって明るく幸せに満ちた年でありますよう、御祈願申し上げます。
では本日からは、物理に関する内容をお届けします。大晦日の更新なのに新しい分野に移り恐縮ですが、皆様お付き合いくださいませ。まずは、本日からお届けする物理の内容に関して、アドバイスや情報を提供して下さったS先生のことを簡単にご紹介します。
Q.先生の学歴は?
A.九州大学理学部物理学科
Q.先生の指導歴は?
A.大学受験にかかわる物理が25年間、大学受験の化学と数学に関しては少なくとも10年間
Q.先生の趣味は?
A.趣味はポピュラー音楽鑑賞。そして、片道1時間かけて自転車で通勤するくらい、よく自転車に乗っています。普段から自転車に乗ってあちこち出かけ、写真を撮ったりしています。東京の多摩地域は、随所に大きな公園などがあるので、あちこち行く甲斐がありますね。九州で育った私には、とても新鮮です。又、国内旅行も趣味です。今はコロナなので、自宅でテレビを見ることを一番よくやっています。
Q.先生の、子供の頃の夢は?
A.電車を運転したかったのが、子供の頃の夢でした。鉄道は、ずっと長く続けている薄い趣味です。
Q.先生の、休日の過ごし方は?
A.休日は、何回も行った場所でも改めてあちこち回って、写真を撮ったりしています。東京都内だけでなく、多摩地域から自転車で行ける埼玉の川越や所沢などを含みます。できれば、国内に絞りつつ長野や北陸など遠方まで小旅行に出かけたいのですが、コロナの日々ですし、東京近郊を自転車で回ることが多いですね。
Q.先生が入っていた部活やサークルは?
A.高校で1年間、合唱をやってました。
Q.先生が指導なさっている教科名を教えてください。
A.大学受験の物理
Q.指導した生徒の合格実績を教えてください。
A.東京医科歯科大学医学部医学科、北海道大学医学部医学科、弘前大学医学部医学科、鳥取大学医学部医学科、横浜市立大学医学部医学科、東京慈恵会医科大学医学部医学科、日本医科大学医学部医学科、順天堂大学医学部医学科、慶應義塾大学医学部医学科、昭和大学医学部医学科、東邦大学医学部医学科、杏林大学医学部医学科
上記の情報からも、アウトドアの気さくな性格で、受験ノウハウが豊富で、情熱的な指導をなさる先生である事がうかがわれますね。私も東京の多摩地区に住んでいて、あちこちサイクリングするのが好きなので、S先生にとても共感します。どこへ出かけても、東京郊外の多摩地区や埼玉南部は、豊かな自然や新鮮な風景に出会うことができるのですよね。
では、受験勉強に関する本題に入っていきますね。
Q.物理の学習法でオススメのものは、なんですか?
A.とにかく多くの問題を解くことです。それに尽きると思います。
自力で解くだけでなく、多くの問題に触れて多くの問題を経験することです。カリキュラムが一通り終わった人は、何もしないよりは、問題と解答解説を照らし合わせるだけでも1つの学習法といえます。ただし、問題と解答解説を読んで理解を深められるのは、カリキュラムを一取り終えた人だけです。このように、生徒一人ひとりに直接あたってみないと分かりにくいところです。どんな生徒にも通用する学習法が、とりわけ初学者には見当たらないので、生徒次第と言えます。アテナイにお越しいただければ、生徒一人ひとりの現状学力にピッタリ合ったカリキュラムを作成いたします。
やはり、物理も数学と同じく、多くの問題を実際に解くこと、そして能動的に多くの問題にあたって多くの問題を経験していかなければならないのですね。豊かな経験に勝るものなし、といったところでしょうか。逆に言えば、受動的に講義を聞いているだけでは、なかなか学力が付かないという事ですね。自ら多くの問題に体当たりして初めて、血となり肉となり、ということです。
では次回は、「物理のオススメの参考書は? 定期テストで赤点を取る人の物理の学習法とは?」などのテーマでお届けします。ご期待ください。
投稿者プロフィール

- 根っからの語学マニア。大学院では、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ラテン語、古典ギリシャ語、韓国語を学んだ。日本にいる外国人と外国語で話すより、現地の国へ行って外国語で話すのが好き。
最新の投稿
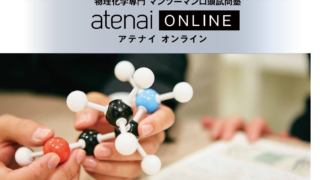 勉強法2022.03.04実際の入試問題を解く際の口頭試問の使用例とは?
勉強法2022.03.04実際の入試問題を解く際の口頭試問の使用例とは? 勉強法2022.02.25理系受験生を本心から応援する「三つ子の魂百まで」の私の理由
勉強法2022.02.25理系受験生を本心から応援する「三つ子の魂百まで」の私の理由 勉強法2022.02.18教材のコンセプトと口頭試問の関わり
勉強法2022.02.18教材のコンセプトと口頭試問の関わり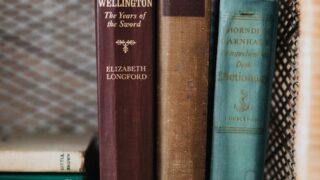 勉強法2022.02.11口頭試問の全体的な意図とカリキュラムにおける使用役割
勉強法2022.02.11口頭試問の全体的な意図とカリキュラムにおける使用役割