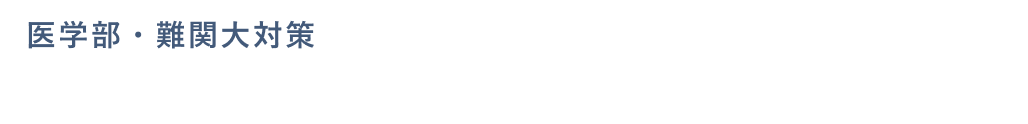アリストテレスが残した「至極の名言」偉人について学ぼうシリーズ(2)
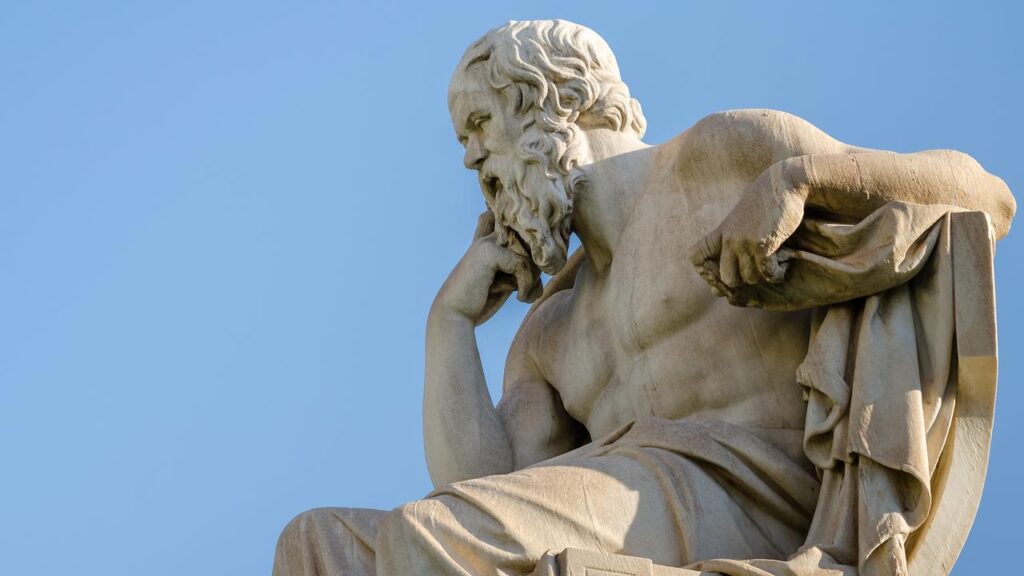
多岐にわたる自然研究の業績から、「万学の祖」と形容される、古代ギリシアの哲学者アリストテレス。今から2,300年以上も前に生きていたとされる彼ですが、その発言が現代を生きる私たちにとって、有益なアドバイスとなることも少なくありません。
この記事では、そんな彼がどんな人だったのか、そして彼が残した多くの名言を紹介します。
ものごとの本質を鋭く突く彼の名言は、読めば読むほど深くあなたの心に染み入るはず。
お気に入りの名言を見つけ、人生の道標にしてみませんか。

アリストテレスとは?どんな人? 生い立ち・生涯・経歴を紹介
17歳でプラトンの弟子になる
アリストテレスは紀元前384年にトラキア(現在のブルガリア、ギリシャ、トルコ周辺)で生まれます。父親のマルコスは当時この一帯を支配していたマケドニア王国に仕える医師でした。
しかしアリストテレスが小さい時に両親は亡くなってしまい、その後は義理の兄と一緒に生活していたと言われいています。
17歳頃から有名な哲学者プラトンがつくった学校であるアカデミアに入学します。師となるプラントからは「学校の精神」とまで評価され、教師として生徒に教えることもありました。
アレクサンドロス大王の家庭教師
その後プラトンが亡くなるまでの約20年間をこのアカデミアで過ごしたと言われています。
プラトンが亡くなると、甥であるスペウシッポスが校長に選ばれます。これと同じくらいの時期にアリストテレスは学校を辞め、友人がいるアッソスという町に移住します。
その後マケドニアの王子、アレクサンドロスの家庭教師に選ばれると、それがきっかけで自分の学校も作り、文学、科学、医学、哲学などを教えていました。
万学の租、様々な学問を探求する
アリストテレスは「万学の租」と言われるくらい、哲学だけでなく自然学や政治学、動物学など様々な学問に精通していました。
現代学問にも大きな影響を与えているアリストテレスですが、特にイスラム文明に多大な影響を与え、イスラム科学の礎を築いたとも言われています。
アリストテレスは人間の本性は「知を愛する」ことにあると考えました。ギリシア語でこれをフィロ(愛する)ソフィア(知)と呼び、この言葉がのちに哲学(フィロソフィ)の語源ともなりました。
アレクサンドロス大王が亡くなり逃亡生活
アレクサンドロスが無事に王に即位した次の年に、アリストテレスは49歳でアカデミアがあるアテナイに戻り、そこでも学校を開設します。
彼はたくさんの弟子を持ち、学校も繁栄していきます。その後閉鎖されるまでアカデミアに並ぶ学校とされていました。
その後アレクサンドロス大王が亡くなると、マケドニア王国の力も同時に衰え始め、マケドニア人に対する迫害が起こります。アリストテレスも逃げるように母親の故郷に移住し、その後病気になったと言われています。
そして紀元前322年に62歳でこの世を去りました。

アリストテレスが残した名言
では、アリストテレスは生涯でどんな名言を残したのでしょうか。
何かを学ぶとき、実際にそれを行なうことによって我々は学ぶ。
いわゆる、「習うより慣れろ」ってやつですね。とりあえず、行動することが大切なのだと。
勉強のスケジュールを建てるのも大切ですが、とりあえず手を動かしてみないと見えてこないものもたくさんあります。
どうすればいいんだろうと迷ったときには、目の前の課題ややるべきことを盲目的にこなしてみましょう。
我々の性格は、我々の行動の結果なり。
寝坊して遅刻しがちな私には、とても耳が痛い名言です笑。
性格というのは、日々の行動の連続の先にあるものである、というのがアリストテレスの考えです。
「どうして私はこんな性格なんだろう。」「悩みがなさそうなあの人が羨ましい」など思ったことはありませんか。
そんな楽観的な性格でも、逆に真面目な性格だとしても、行動が先んじるのです。
楽しそうにしてるから楽観的に見えるし、勤勉に勉強や仕事をしているから真面目な性格と思われるし、自分でもそう思うのですね。
人に従うことを知らないものは、よき指導者になりえない。
新入社員や新人として仕事やサークルなどの活動を行うとき、自分のやり方のほうが効率が良い!と言って、上の人に従わないような人をたまに目にします。しかし、それでは上に立つものにはなれないとアリストテレスは言っています。
それはなぜか。
ひとつに、人に従って行動したことがなければ、上の立場になったときに従う側の気持ち(プレイヤーとしての気持ち)がわからないからでしょう。過去に自分が、同じように人に従って行動していれば、その時に感じた気持ちや持った悩み、苦悩があるでしょう。
従うものがゆえのそういった悩み事、人に気づいてもらいたいことを、予めわかっているということは、そのグループをまとめる上で大きな武器となります。
ふたつめに、上の立場の人は長年そういったことをしてきた人がほとんどですから、新人が考えるような工夫はだいたい考えた事があるのです。
それでも、今の体系があるのですから、なにか理由があってブラッシュアップされたのがその形であることが多いのです。
世間が必要としているものと、あなたの才能が交わっているところに天職がある。
才能がある人って羨ましいな。そう思ったことが誰しもあるでしょう。
私達がほしいと考える才能とは、「お金につながる才能」だとか「多くのひとから尊敬されそうな才能」であることが多いのです。
人にはそれぞれ得意、不得意があります。
自分は平凡な人間だから、と思っている人にも、実は気がついてないだけで磨けば人から尊敬されたり、お金を稼ぐことに繋がる才能が埋もれていることはたくさんあります。
迷ったときにはチャレンジしてみる、という気持ちが大切です。
人はものごとを繰り返す存在である。つまり優秀さとは、行為でなく習慣になっていなければならないのだ。
行動が性格を形作ると言っても、一回や二回の行動で人は変わりません。
変わりたければ、その行動を習慣にすることが、大切なのです。
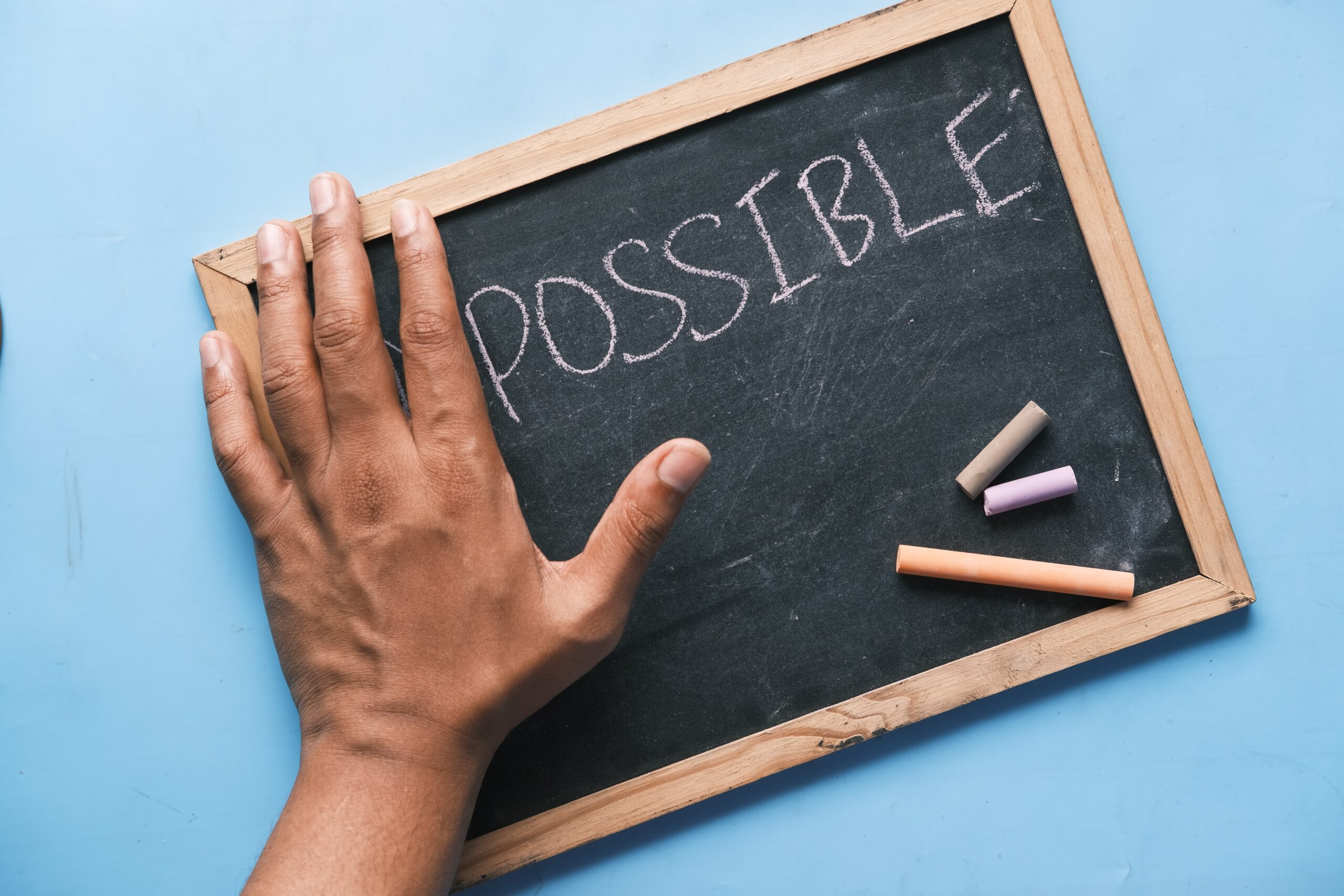
言葉から見た、アリストテレスてこんな人!
2000年以上前に生きたアリストテレスは哲学だけでなく、さまざまな学問に精通する人物でした。
彼は生れながらに優秀なわけではなく、日々の学びの積み重ねが多くの知恵を彼に与えました。
それはアリストテレスの「美徳と優秀さを持っているから正しく行動するのではない。むしろ正しく行動するから美徳と優秀さを持つ事ができるのである」という言葉からも感じ取れます。
また「何かを学ぶとき、実際にそれを行なうことによって我々は学ぶ。」という言葉にもあるように、知識だけにとどまらず行動、体験から「生きた知」を手に入れていました。
自らの行動により学問を得た人。それがアリストテレスでした。
より詳しい生涯のこと、どんな学問を発展させたのか、といった細かいところまで紹介している記事があったので参考に貼っておきます。
過去の偉人やその名言から、自分に活かせることを見つけ、有効活用していきましょう!
投稿者プロフィール

-
チェスと筋トレが趣味の国立医大生。
最近ゴルフもはじめました。物理や化学を中心に、受験生がつまづきやすいような項目について、わかりやすく解説していきます。
最新の投稿
 勉強法2022.03.31これで間違いなし!おすすめ化学参考書5選
勉強法2022.03.31これで間違いなし!おすすめ化学参考書5選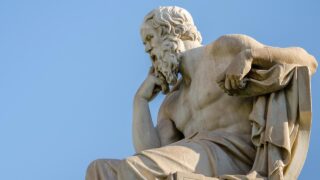 偉人2022.03.31アリストテレスが残した「至極の名言」偉人について学ぼうシリーズ(2)
偉人2022.03.31アリストテレスが残した「至極の名言」偉人について学ぼうシリーズ(2)  勉強法2022.03.29検証!今話題の口頭試問を、化学を5年間やってない医学生が受けてみた!(後編)
勉強法2022.03.29検証!今話題の口頭試問を、化学を5年間やってない医学生が受けてみた!(後編) 勉強法2022.03.29検証!今話題の口頭試問を、化学を5年間やってない医学生が受けてみた!(前編)
勉強法2022.03.29検証!今話題の口頭試問を、化学を5年間やってない医学生が受けてみた!(前編)