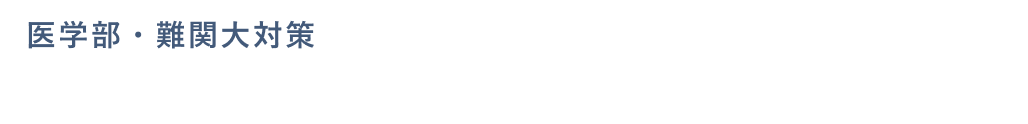コツをつかんでラクラクマスター!化学反応式の使いこなし方

全国で雪が本格的にふりはじめました。私の住む地域でも初雪を観測し、冬の厳しい寒さに耐える日々が続いております。本日もAtenaiメディアを読んでいただいてありがとうございます。ライターのTakataです。みなさんの今年の一年の目標は何でしょうか。目標を持って行動することで、モチベーションも上がりますし、集中力も上がります。ぜひ、叶えたい目標を具体的に言葉にしてみましょう。
さて、今回のブログのテーマは「化学反応式」についてです。前回と前々回の記事で、「化学式」と「元素記号」について一緒に勉強しました。
「化学式」の記事はこちら
「元素記号」の記事はこちら
この記事では、化学反応式とはなにか、ということから作り方、テストに出る覚えておきたい化学反応式まで、ひとつひとつ丁寧に紹介します!
・化学反応式とは何か
まず、化学式とは、「ある物質は何の原子が何個ずつで集まってできているかを示している式」のことでした。このように物質を化学式で表すと,化学変化も化学式で表すことができます。化学変化を化学式で 表した式を化学反応式といいます。
2H2O → 2H2 +O2
化学反応式は数学で出てくる式とは少し違い、左側と右側が矢印で繋がれています。ここを=とすると間違いですので、気をつけましょう。
なぜ=ではなく、→なのかというと、化学変化には向きがあって、今回の化学
変化は左側の物質から右側の物質に変化するということを表しています。
右側の物質から左側の物質に変化することは考えないので、一方通行の→マークが使われているのです。
・化学反応式のつくりかた
では、一緒に化学反応式を作ってみましょう。ここでは、
「水を分解したら、水素と酸素が発生した。」
という化学変化を化学反応式で表してみます。
①反応前の物質は何と何か、反応後の物質は何と何かを読みとる。
この場合、反応前…水だけ 反応後…水素と酸素
水→水素と酸素と表しておくとわかりやすいと思います。
②物質名を化学式で表す。
物質をそれぞれの化学式で表してみましょう。
水はH2O、水素はH2、酸素はO2だから
H2O → H2 + O2
となります。
③→の左辺と右辺でそれぞれの種類の原子の数を合わせる。
H2O → H2 + O2 を分子モデルで考えてみましょう。
右辺のOが1個多いので、左辺のH-O-Hを1つ増やす。
右辺のHが2個足らなくなってしまったので、右辺のH-Hを1個増やす。
これで反応前と反応後で、すべての種類の原子の数がそれぞれそろいました。
反応前は水分子2個、反応後は水素分子2個、酸素分子1個なので、これを元の化学式にすると…
2H2O → 2H2 +O2
これで完成です!
他の化学反応でも同じように、
①反応前の物質は何と何か、反応後の物質は何と何かを読みとる。
②物質名を化学式で表す。以後、化学式の形は変えないようにしましょう。
③左辺(→の左側)と右辺(→の右側)でそれぞれの種類の原子の数を合わせる。
というステップをふむことで、化学反応式を作ることが出来ます。
③のステップがなれるまでは大変ですが、焦って頭の中でやらずに、今回のように図を描いて行うことが、正しい化学反応式をつくるポイントです。何回もやってるうちに、ここは省略できるな、など工夫をすることができるようになるので、最初はゆっくり、確実に化学反応式をつくることを心がけましょう。
・これはテストに出やすい!覚えておきたい化学式
自分で化学反応式をつくれるようになった方向けに、よく問題として出てくる化学反応式を紹介していきます!
【さまざまな分解】
・水の電気分解
2H₂O→2H₂+O₂
・炭酸水素ナトリウムの(熱)分解
2NaHCO₃→Na₂CO₃+H₂O+CO₂
・酸化銀の(熱)分解
2Ag₂O→2Ag+O₂
【硫黄と結びつく化学変化】
・鉄と硫黄の反応
Fe+S→FeS
・銅と硫黄の反応
Cu+S→CuS
【酸化・燃焼】
・銅の酸化
2Cu+O₂→2CuO
・マグネシウムの燃焼
2Mg+O₂→2MgO
・有機物の燃焼
C+O₂→CO₂ ,2H₂+O₂→2H₂O
※メタンの燃焼 CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O
【還元】
・酸化銅を炭素によって還元
2CuO+C→2Cu+CO₂
・酸化銅を水素によって還元
CuO+H₂→Cu+H₂O
【その他】
・炭酸水素ナトリウムと塩酸の反応
NaHCO₃+HCl→NaCl+H₂O+CO₂
・石灰石(主成分は炭酸カルシウム)と塩酸の反応
CaCO₃+2HCl→CaCl₂+H₂O+CO₂
その他以外は、どれもよく出てくる化学反応式です。作り方を覚えていれば、その場で作ることも出来ますが、テストや問題集で何回も出てくるので自然と覚えてしまうと思います。試験対策としては、10個だけなので覚えちゃうのが確実です!
今回は化学反応式について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
最初は戸惑うところもあるかと思いますが、慣れてスラスラ化学反応式を作れるようになると、大きな得点源になります!
何回も繰り返し問題演習をして、自信をつけていきましょう!
投稿者プロフィール

- 根っからの語学マニア。大学院では、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ラテン語、古典ギリシャ語、韓国語を学んだ。日本にいる外国人と外国語で話すより、現地の国へ行って外国語で話すのが好き。
最新の投稿
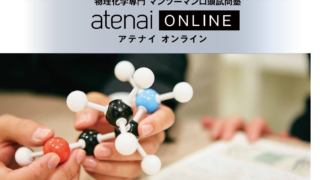 勉強法2022.03.04実際の入試問題を解く際の口頭試問の使用例とは?
勉強法2022.03.04実際の入試問題を解く際の口頭試問の使用例とは? 勉強法2022.02.25理系受験生を本心から応援する「三つ子の魂百まで」の私の理由
勉強法2022.02.25理系受験生を本心から応援する「三つ子の魂百まで」の私の理由 勉強法2022.02.18教材のコンセプトと口頭試問の関わり
勉強法2022.02.18教材のコンセプトと口頭試問の関わり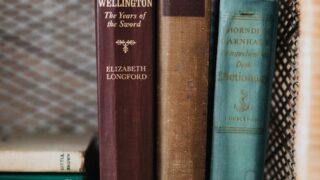 勉強法2022.02.11口頭試問の全体的な意図とカリキュラムにおける使用役割
勉強法2022.02.11口頭試問の全体的な意図とカリキュラムにおける使用役割